皮膚が赤く腫れる(蜂窩織炎)

約1ヶ月ぶりのブログの更新となります。
今回は皮膚の病気を取り上げようと思います!
皮膚の病気も色々ありますが、今回取り上げるのは『蜂窩織炎(ほうかしきえん)』です。
聞きなじみがないかもしれませんが、500人に1人が蜂窩織炎を発症するとも言われています。内科の外来診療をしている中で、ときどき出会うことのある、意外と多い皮膚の病気です。
蜂窩織炎とは
蜂窩織炎は、皮膚の深い部分(真皮~皮下脂肪組織)で生じる感染症です。
つまり、何らかの原因で細菌が皮膚の深い部分に入り込み、炎症を引き起こす病気です。
下肢(特に膝下)で起こすことが多いのですが、基本的には体のどの部分でも起こります。
原因は”傷”のことが大半

ブドウ球菌や連鎖球菌といった細菌が皮膚の傷から入り込むことで発症します。
例えば、引っかき傷・虫刺され・すり傷などが原因となることが多いです。また侮れないのが、足白癬(いわゆる“水虫”)です。足白癬で指の間の皮膚がむけると、その部分から細菌が侵入することがあるのです。
ただし、明らかな皮膚の傷がなくても蜂窩織炎を起こすこともあります。
皮膚が赤く腫れて痛くなる
感染を起こした部分の皮膚が赤く腫れあがり、その箇所に痛み(触ると痛い)と熱感(皮膚が熱っぽい)がみられます。また、発熱や倦怠感を伴うこともよくあります。多くの場合は、体の片側のみに皮膚症状が出るのが特徴です(例えば、左足だけといった具合です)。
「この病気はうつるんですか?」と尋ねられることがありますが、蜂窩織炎はヒトからヒトには感染しません。
糖尿病の方は特に要注意!
蜂窩織炎に特に注意していただきたいのは、「糖尿病治療中の方」や「免疫力が低下している方」です。
例えば、糖尿病のコントロールが悪い方では、蜂窩織炎の発症リスク・重症化リスク共に高まることが分かっています。また、他の病気に対してステロイドを内服中の方や、抗がん剤治療中の方も免疫力が低下しているため注意が必要です。
そして、食事があまり摂取できず、栄養状態があまり良くない方も免疫力が低下していることが多く注意が必要です。以前の記事(サルコペニア)でもお伝えしましたが、“低栄養”は全身の筋力低下から転倒・骨折のリスクにも繋がるため、早めの対応が必要と考えられます。
蜂窩織炎の診断・治療
多くの場合、皮膚の診察と血液検査のみで診断可能です。
治療は抗菌薬です。軽症であれば飲み薬で改善することが多いのですが、重症の場合は入院での点滴治療が必要となる場合もあります。また飲み薬で治療を始めたものの症状がなかなか良くならないケースでも、点滴の治療が必要となることがあります。
特に、前述した「糖尿病治療中の方」や「免疫力が低下している方」では重症化しやすいため、より慎重な対応が必要とされています。
保湿で皮膚バリア機能を保ちましょう
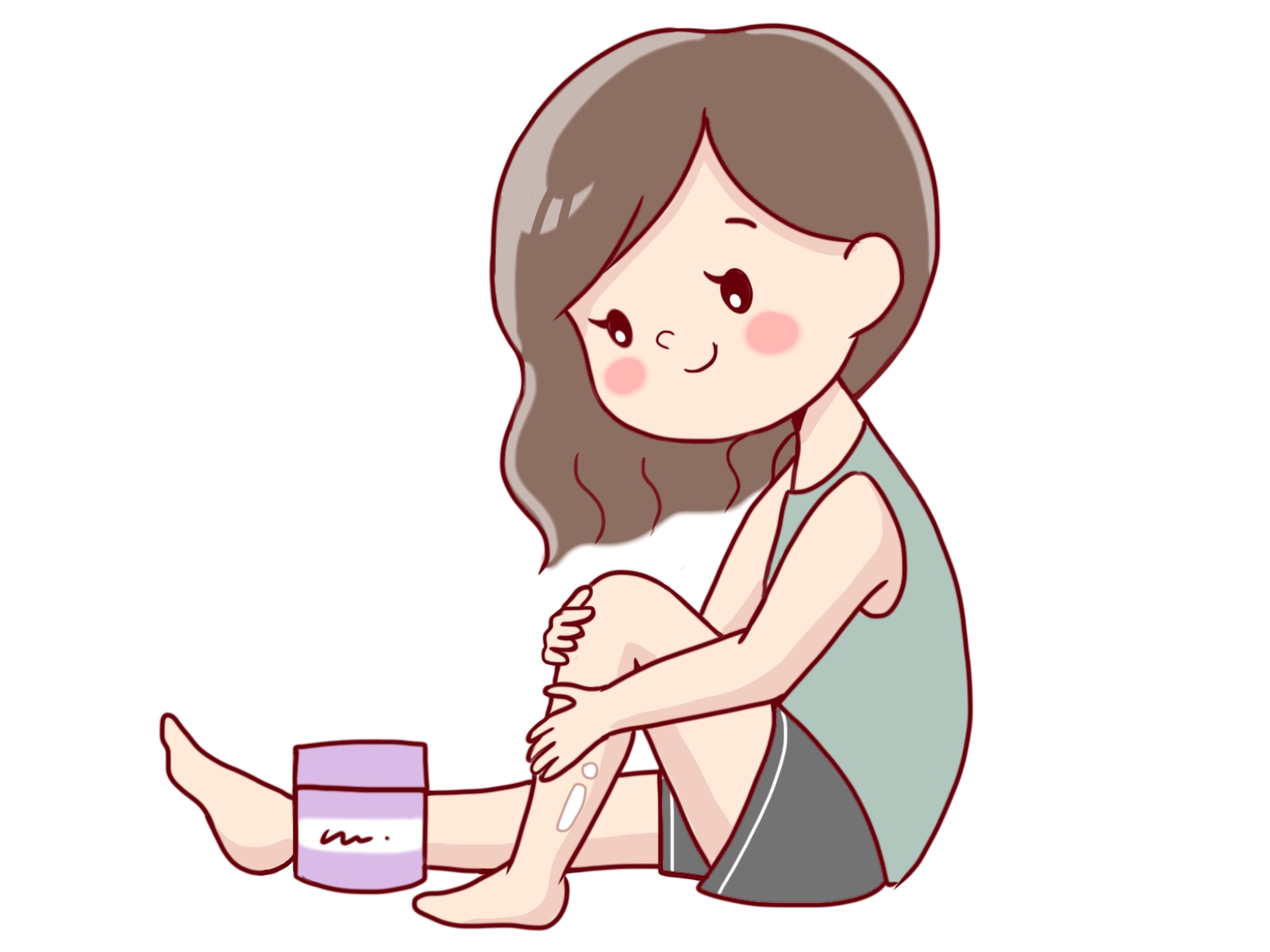
皮膚のバリア機能を保つことが大切です。お風呂上がりなどに保湿剤を塗って、皮膚を保湿する事がおススメです。特に冬場は皮膚が乾燥しやすいので、ぜひ定期的な保湿をおこなうようにしてください。
また、足白癬(水虫)やアトピー性皮膚炎がある方は早めに治療を開始することが予防にも繋がります。
そして、体の免疫力を上げることも重要です。そのためには、1日3食のバランスの良い食事や規則正しい生活(十分な睡眠や適度な運動)を心掛けてください。なかなか食事が進まないという方には、当院から栄養剤(カロリーの高いドリンク)を処方し、食事だけでは足りない栄養を補うことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
今回は、急に皮膚が赤く腫れあがる病気『蜂窩織炎』についてお伝えしました。
虫刺されと思っていたらだんだん皮膚が赤く腫れあがってきた場合は、蜂窩織炎を疑う必要があります。軽症であれば飲み薬で治る場合も多いので、早めの受診をお勧めいたします。
当院は、総合内科専門医として幅広い病気を診療しておりますので、何か気になる症状がございましたらお気軽にご相談ください。
関連記事はこちら〉〉 サルコペニア(筋力低下)
高血圧・糖尿病・脂質異常症などでお悩みの方は、東広島市西条町助実の内科・呼吸器内科・アレルギー科の『西条すこやか内科』までお気軽にご相談下さい。
西条すこやか内科
院長 奥本 穣(呼吸器専門医・総合内科専門医)
